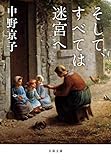「看護師」はひと昔前なら「看護婦」。神話の時代からある仕事とは? 「リケ女」のはしりは命がけ! 知っているようで知らない、仕事のルーツや歴史を、『怖い絵』シリーズの中野京子が解説。今まで見えてこなかった、もうひとつの西洋史がそこにある。
収録された絵画、全50点。中世から現代アメリカ絵画まで、幅広いラインナップと驚きのストーリーが「見る」西洋史の世界へ誘います。
<内容>
闘牛士 ── 動物虐待か、スポーツか、はたまた神事か
侍女 ── 宮廷の奥深くに入り込む「侍女は見た」!?
香具師 ── 今も昔も変わらぬ騙し騙されの世界
宮廷音楽家 ── ライブが全てだった時代特有の苦労
羊飼い ── 社会のアウトサイダーにならざるを得なかった
女性科学者 ── 「リケ女」のはしりは命がけ
道化 ── 舞台でおどけて、楽屋で泣いて
警官 ── 絵画の主役にはなりにくい役回り
思想家 ── 簡単なことを難しく考えるのが仕事?
ファッション・デザイナー ── 衣装を見れば時代がわかる
大工 ── イエスと結びつき、神聖化された職業
看護婦 ── プロフェッショナルと認められるまでの長い道のり
政治家 ── ヘンリー八世に仕え、明暗をわけた政治家たち
修道女 ── 神に捧げる一生ですら時代に翻弄されて
船頭 ── 神話世界から続く職業も今や先細り
異端審問官 ── 泣く子も黙らせ、良い子も騙すテクニック
傭兵 ── 世界最古の男の仕事。舞台は戦場
女優 ── 女はもともと演技上手。その最高峰が……
子どもも働く ── 厳しい環境を逞しく生き抜く
天使も働く ── 人間のためではなく神のために働くのは当然
仕事の視点で絵画を見ると言うのが面白かったです。
中には見たことのある作品もありました。
女性科学者の絵は見た事があって、どうして身ぐるみをはがされて恐怖の表情をしているのか、分かった時につらかったです。看護婦という言葉を久しぶりに聞きましたが差別用語になってしまうんですね…。黒のチョーカーを身に着けている看護婦さんの絵も見た事があって、美しいなと思っていました。
読んでいてつらい内容の絵画もありましたが、面白く読みました。
<集英社 2022.9>2024.2.22読了